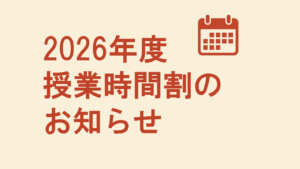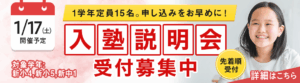宮沢賢治『やまなし』に登場する謎に満ちた言葉「クラムボン」。
小学校国語の中でも特に掴みづらい物語であると同時に、思考力・創造力・説明力を磨く絶好のチャンスなので、クラムボンを考えるきっかけになる動画を作成しました!
このブログでは、実際に川崎学舎の小学6年生と『やまなし』の授業をした際の様子も取り上げているので、ぜひ最後まで目を通していただければ嬉しいです。
クラムボンが出てくるシーン
※読みやすく改変しています
2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していました。
「クラムボンはわらったよ。」
「クラムボンはかぷかぷわらったよ。」
「クラムボンは跳ねてわらったよ。」
「クラムボンはかぷかぷわらったよ。」
上の方や横の方は、青くくらく鋼のように見えます。そのなめらかな天井を、つぶつぶ暗い泡が流れて行きます。
「クラムボンはわらっていたよ。」
「クラムボンはかぷかぷわらったよ。」
「それならなぜクラムボンはわらったの。」
「知らない。」
【中略】
「クラムボンは死んだよ。」
「クラムボンは殺されたよ。」
「クラムボンは死んでしまったよ……。」
「殺されたよ。」
「それならなぜ殺された。」
兄さんのカニは、その右足の4本の脚の中の2本を、弟の平べったい顔にのせながら言いました。
「わからない。」
魚がまたツウと戻って下流のほうへ行きました。
「クラムボンはわらったよ。」
「わらった。」
にわかにパッと明るくなり、日光の黄金は夢のように水の中に降って来ました。
クラムボンの可能性5つ
「泡」
小学校の頃のクラスでは「泡」がクラスの結論でした。
会話の合間に「つぶつぶ暗い泡が流れて行きます」と書いてありますし、可能性は十分 にありますよね。
また、カニは泡を吐き出すイメージもあります。さらに、水の中で現れたり消えたりするのも泡の特徴なので、「死んだ」「殺された」から再度「わらった」となる流れにも納得することができますね。
「川底の生き物」
エビ・サワガニ・カゲロウ・プランクトンのような小動物という仮説です。
もう少し大きな動物に捕食されることによって「殺されてしまった」と思ったら、実は逃げていて生きていて、その様相を「笑った」と表現している可能性もありますよね。
宮沢賢治の他の小説の中でも、昆虫が登場することがあるので、川底の動物たちのことを総称してクラムボンと呼んでいるかもしれませんね。
アメンボと、アメンボが移動することによって生じる泡を合わせて「クラムボン」という可能性もあるのかも?
「二枚貝の子ども」
二枚貝=clam(クラム)
子ども=坊(ぼん)
を合わせたという仮説ですね。
方言で「坊(ぼん)」を「子ども」と表現する地域があるそうです。
「かぷかぷわらう」という表現にも合うので、二枚貝の子どもと言うことも出来るのではないでしょうか。
「感情」
希望が湧いては消える。
不安がチラついては、遠のく。
のようにクラムボンという名称の感情があり、その感情が現れたり、消えたりするという仮説です。
目に見えないものなのに、兄弟ふたりで共有している感覚というのは、子どものうちにしかない発想かなあと思うので、個人的には好きですね。
「光」
(目が)眩む
盆=まるいもの
という由来から、太陽や月の「光」なのではないかという説もあるようです。
雲によって光が見え隠れする様子を「わらう」「死ぬ」と表現したのかもしれませんね。
宮沢賢治が関心を寄せていた法華経でも、光は非常に重要視されたいたので、と根拠のある考察をしている論文も拝読しました。
川崎学舎で出た面白い意見
川草・魚が水面に触れるときの丸い輪など、面白い意見はいくつもあったのですが、特に僕が心惹かれた意見は「地球」です。
小学6年生のちょっとシュールな男子が語ってくれた仮説です。
実は、宮沢賢治はカニを1番強い動物と設定しており、川底で虎視眈々と地球の表面上を眺めているというのです。
恐竜がいた時代に、隕石が落ち生物が居なくなるものの、時を経てまた動物たちが復活する様子をカニの親子が観察していると考えたというのです。
時間と空間のスケールを人間感覚から超越した意見に、僕は思わずどうコメントして良いものかと考えてしまいました。
話してくれた普段の彼は、論理的でクールだからこそ、そんなファンタジーも出せるのかとギャップに感動した節もあります。
数日間、考え込んでしまいましたね。
宮沢賢治作品の魅力
日本の教育で求められる能力として、「再現する力」がまだまだ根強いですよね。
川崎学舎で作文を教えていると、自分の経験を考察することで何かの示唆を引き出すという、ある種の創造的な取り組みが苦手な子どもたちが多いことを実感します。
単調に感じてしまう勉強内容でも、漢字や計算方法を覚える方が簡単ではあるんですよね。
そういった行為に高い点数が付きやすい環境にいると「つまらないけど、まあ覚えれば良いか」という風に思うことは普通だと思うんです。
だからこそ、宮沢賢治『やまなし』が小学校の教科書に選定され続けていることを、僕は嬉しく思っています。
岩手県の農業の難しさという現実に頭を悩ませる過程で、思考の拠り所は童話や詩にも移行していく。
現実と空想が行き来する文体は、賢治の生き様をそのまま反映しているようで、読者は不思議な気持ちで物語の世界に誘われていく。
教職にも就いていた賢治ですから、子どもたちに向けたメッセージもきっと残しているはずです。
『やまなし』を読み解くとき、他者を論破できるほど完璧な理論を練り上げることは重要ではないと思います。
ですが、よく分からないなりに、それでも理由をつけて「クラムボン」は何だろうと思考を巡らせる過程は重要だと思います。
日本の教育では珍しい、思考・創造・表現が強く求められている単元だと思いますし、塾でありながらも丁寧に取り上げてよかった学校教材だなと振り返っています。
川崎学舎の小学生たちには、深くて面白い思考を身につけてほしいなと常々思っています。